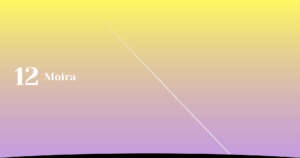誇り高きボミゴケ
チャツボミゴケ
チャツボミゴケとは一体何なのか。
その問いに答える声はない。奴は、チャ・ツボミ・ゴケかも知れぬし、チャツボ・ミ・ゴケやも知れない。チャツ・ボミゴケの可能性だってあるのだ。ボミゴケ。なんていい響きだ。なんとなくぐちゃっとして、美味しくないのが分かる。意味は分からないけれど言われたらムカつく。この世にまだ無い罵声のような響きがある。なんて言ったって、吐き捨てるように言うのが一番気持ちがいい。それがボミゴケ。逆から読んでもいい味がしている。あなたは呆れている暇があるなら、声に出すべきだボミゴケを。それだけではない。パーツは知っているのだ。だがその組み合わせは知らない。ジョージクルーニー卵とじ だとか 熱川バナナワニ園 とか東インド会社だとか ハンマーヘッドシャークと同じ胸の高まりが分かるだろう。なぁ。
こうして未知なるボミゴケへの旅、そう、我々のJourney to the Bomigokeが始まった 。
ボミゴケを各々口で転がしながら、山道を進む。森が開けた山間にぽつりぽつりと民家が建ち、その広大な畑の一角に緑のトンネルが一筋通っている。思わず車を寄せれば、蔦はその支柱に雫型の葉を絡ませているのである。その手から逃れるように、兵児帯のような尾をひらりと躱して、朱色の金魚が泳いでいる。脇には幾つかの豆を込めた鞘が下がっていて、そこへ橙の蜻蛉が羽を休めている。なるほど、これはボミゴケではなさそうだ。
邂逅は突然であった。さらに道を進むと突如として「チャツボミゴケ公園はこちら」の文字が現れた。明らかに奴がここに居る。我々は左に旋回し、奴の住処へと足を踏み入れた。
霧雨は朝から我々の上に降りかかっている。専用のバスに乗り換えると、降りた先からは徒歩にて奴に近づいていくことになる。急流の小川を遡るように、山道を登っていく。端には大手を広げたシダや、熊笹が敷き詰められている。その所々にゴロゴロとした岩が転がり、小川を橋で跨いでも森は奥まで続いている。少し泥濘む砂利道を歩きやすいようにと管理人が敷いたゴムマットが私の足音をボミボミに変換する。途端に、鍬形虫がキノコの角で背中を掻いていたり、フキの葉の傘が滴に揺れていたり、せっかちな萩の小さな紫が投げキッスを飛ばしてくるような小道になる。ボミゴケは近い。
ボミボミロードから木組みの遊歩道に乗り換える。熊笹の先に、奴が見えた。
森は突如開かれ、黒と橙、そして目を見張るような緑がモザイク模様を成している。それぞれのコロニーの中心は黒く、すこし焼いた炭のように灰がちで、橙の岩肌が顔を覗かせる。その外側の緑は劇場の座席カバーのように、上質な光沢と柔らかさで、綿がたっぷり詰まっていているほどにふっくらしており、光の角度によっては銀色に艶めいている。それらを縁取る様に幾筋もの水の流れが岩肌を舐めるように滑っている。この、緑である。
さらに遊歩道を進むと、熊笹の中に小川の源流の一つを見つける。くぼみに澄んだ水が湧き上がり、時折気泡が浮かび上がってくる。沈んだ笹の枝や落ち葉が白く染まって沈んでいる。それだけで無く、その水に触れている一帯は、岩でも草でも白く染まっている。その水が小川の本流と混ざり合い、先ほどのビロードへ流れ込んでいる。
白根火山の爆発によりできたすり鉢状の穴が我々が見た開けたモザイク状の絨毯である。そこにあの白い泉から湧いた硫酸酸性の鉱泉が流れ込んでいる。この穴に落ちた生物は生きては出られない、穴地獄であるが、そこに繁るのが強酸性の温泉水が流れる土地に生息する希少な苔 チャツボミゴケ(苔類 ツボミゴケ目 ソロイゴケ科:Solenostoma vulcanicola)である。世界にある18000種のコケ中で最も強いと言われる耐酸性が、あの目を見張るような緑を呈していたのだ。
鉱泉の湧き出し口から約400mの範囲はpH3以下の強酸性を示し、水温は25℃前後で雪降りしきる冬季も暖かく、年間を通じて高水温が維持されている。白い泉の付近は硫化水素が強く群生は見られないが、泉の淵が白いように、水中の硫化水素が酸化され硫黄の白い沈殿を生じ始める湧出口から数m離れた場所からは、彼等の雄志がはっきりと見て取れるのだ。
また、この鉱泉は硫酸イオンや塩化物イオンの他に鉄などの金属イオンが高い濃度で含まれている。この環境を好んで生息するチャツボミゴケと鉄バクテリアの生物活動の副産物として、鉄鉱が生成されている。バイオミネラリゼーションである。
魚の鱗、海老や蟹の殻 、真珠、珊瑚。我々の歯や骨もこの営みによるものであり、悠久の時を経て我々は宝石となる。その輝きは孔雀や玉虫、モルフォ蝶のように、その構造由来の輝きは色素や顔料のように退色することなく、誰かの耳に詩となって還ったりするのである。
現存する地球上の約 4,600 種の鉱物種は、地球創成時からあったわけでなく、約25億年前、酸素生成/光合成による酸化的環境が地球にもたらされたことによる生命活動によって 飛躍的に増えたという“Mineral Evolution”(鉱物の進化)があった可能性をR.Hazen,et al.(2008)が提唱するように、チャツボミゴケと鉄バクテリアのような生物の営みによって鉄鋼床は生み出されたのかもしれない。やがて、鉄器時代の訪れが技術革新により人類に富をもたらし、その偏在によって国家が成立していった我々人類の文明史を刻むのであれば、この誇り高き緑こそチャツボミゴケである。
参考
中之条町HP「六合チャツボミゴケ生物群集の鉄鋼生成地保存計画書」
長澤寛道、「もの」が語るバイオサイエンス-10「バイオミネラリゼーションの科学」生物と化学Vol.42,No.5、2004